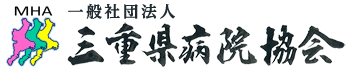2025.9.9 高見山に源を発し、伊勢湾に注ぐ一級河川の櫛田川下流域を空撮してきました。
櫛田川は、奈良時代初期に採掘された丹生水銀や木材の水運・舟運などさまざまな利用が行われ、両郡橋付近には松阪商人の発祥の地である射和商人の古い町並みが残り、櫛田川の清流と調和した独特の雰囲気をかもしだしています。
櫛田川の名の由来は、皇女「倭姫命」が第11代垂仁天皇の命を受け、皇祖神「天照大神」の鎮座地を求めて諸巡行されていたとき、倭姫命が「竹田の国」と呼んでいた地で頭に飾していた櫛を落とされたので、その地に櫛田神社を定め、櫛田という地名もそこから起こったと言われています。
かつて「櫛田の渡し」があり、伊勢街道を往来する旅人が渡し船や馬に乗ってこの川を渡ったと言われており、「南総里見八犬伝」で有名な滝沢馬琴は35歳の初秋、蔦屋重三郎の店で働き、戯作者として頭角を現しつつあった時、上方の文人と交流するためにこの地を訪れているらしい。
その時、馬琴が旅人の心を描いた歌を残している。
「さして行く櫛田の川辺一筋に遅れはせじなかみの都路」
1953年(昭和28年)の13号台風・1959年(昭和34年)の伊勢湾台風により大被害を受けたことから1962年(昭和37年)から国による治水事業が始められました。櫛田川祓川統合頭首工(堰)を可動堰に改築・支川蓮川に蓮ダムの建設等を行い、洪水に対し安全な川づくりが進められています。